保育園に半年だけ通ったあと、小学校へ進学しました。 その頃から、少しずつ「自分の家はほかの家と違うのかもしれない」という感覚が芽生え始めます。
保育園での集団生活の難しさ
半年しか通えなかった保育園では、すでに集団生活に慣れている子どもたちとうまく馴染めず、浮いているような感覚がありました。 時には物理的ないじめを受けることもありましたが、それを誰に相談していいのかも分からなかったんです。
小学校に入って、はっきりとした違和感
小学校へ入学すると、その違和感はさらに強くなりました。 クラス全員に配られる手紙とは別に、私と数人だけに配られる特別な手紙があったんです。
特別な手紙の正体
「おうちの人に必ず見せてください」と言われて渡されるその手紙。 後から知ったのですが、学用品の援助制度や給食費の補助に関する内容でした。 つまり、“貧困家庭”とされる家庭だけに配られていたんです。
鉛筆や消しゴム、絵の具セットなど、学用品を買ったレシートを提出するとお金が返ってくる仕組み。 当時は「え!なんでも買えるじゃん!」と喜んだ記憶がありますが、当然そんな話ではありません。
生活が苦しくなっていくのを肌で感じた
学年が上がるにつれて、生活がどんどん厳しくなっていきました。 祖父母と妹と私の4人暮らし。 母は家にほとんど帰ってこず、祖父母の年金だけが頼りの生活です。
年々苦しくなる生活
学校で必要な学用品が増えるたび、家計は圧迫されました。 家賃や食費だけで精一杯。 やがて、生活費の支払いが追いつかない月が増えていきました。
そして、ライフラインが止まり始めた
最初に止まったのは電話。 3年生の頃、友達からの電話もかけられない・受けられない状況になりました。 「ゆうきくんの家、電話が繋がらないよ」と言われても、当時は笑ってごまかすしかありませんでした。
それが当たり前だと思っていたけれど、今思えばこれが“貧困家庭の現実”の始まりでした。 次回は、ライフラインが次々と止まり、生活がさらに過酷になっていく日々をお話しします。


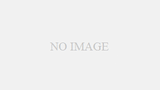
コメント