僕が育った家では、年金というものが話題にのぼることはありませんでした。
というのも、祖父は長年、自営業で小さな飲食店を営んでいたのですが、国民年金を払っていなかったんです。
どうやら「払ってもどうせ戻ってこない」とか「年寄りになってもなんとかなる」といった考えが、当時の祖父の世代には普通にあったみたいです。
子どもの頃の僕は、年金なんて言葉もよく知らず、
年をとったら誰かがお金をくれるんだろうな、くらいの感覚でした。
「なんでうちにはお金がないの?」
小学生のころ、家にはお金がなくて、電気・ガス・水道が止まりまくる家でした。
そんなとき「なんでうちにはお金がないの?」と子どもながらに疑問を抱いたこともあります。
でも誰にも聞けませんでした。
母は日中いないし、ばあちゃんは耳が遠く、じいちゃんも無口でほとんど会話がなかったからです。
今思えば、その理由の一つが「じいちゃんたちが年金をもらえていなかったこと」にあったんですよね。
じいちゃんとばあちゃんは本当に少ない年金で、なんとか僕たち兄妹を育ててくれていた。
その背景を、当時の僕は知ることもなく、ただ「苦しい生活だなあ」とぼんやり感じていました。
転機になった“説明してくれた大人”の存在
転機になったのは、社会人になってからのことです。
ある日、会社の年末調整の書類を書いているときに、年上の同僚がふとこんな話をしてくれました。
「おれの親父も自営業でさ、年金払ってなくて、年取ったらマジで何ももらえないんだよ」
「払ってなかったらそりゃもらえないでしょ。保険みたいなもんだし」
そのとき、じいちゃんの姿と重なりました。
ああ、うちも同じだったんだ、と腑に落ちたんです。
じいちゃんがもらえなかったのは“払ってなかったから”。
そして、自営業は自分で払わなきゃ、何も保証されない世界なんだと。
「年金を払わなかったじいちゃんを、責めたくない」
ただ、決して「年金なんて払うもんか」と言っていたわけではありません。
じいちゃんはきっと、年金制度そのものをよく理解してなかったんだと思います。
当時は、今ほど情報が身近にあったわけでもなく、誰かが教えてくれるわけでもない。
そもそも「払わなかったら、もらえなくなる」という仕組み自体が、じいちゃんにとっては知らない世界でした。
払わなければ制裁があるわけでもない。
だから日々の生活に追われる中で「今は余裕がないから払わない」──そういう“選ばざる選択”を重ねた結果、気づけば何十年と払ってこなかった。
その結果、年をとっても年金をもらえない老後が待っていたんです。
これはじいちゃんだけの問題じゃなくて、情報が届かなかった世代に起きてしまった、ある意味で“制度の落とし穴”のようにも感じます。
サラリーマンの自分が年金を払う理由
僕はいま、サラリーマンとして働いていて、厚生年金に自動的に加入しています。
昔の僕なら「どうせもらえないし、払いたくない」と思っていました。
でも、じいちゃんの生き方を見てきたからこそ、いまは思います。
「払えるなら払っておこう」
「それで将来が少しでもマシになるなら、それでいい」
そしてもうひとつ、これはちょっと感情的だけど――
年金を払わなかったじいちゃんを、心のどこかで責めてしまう自分がいたんです。
だから、自分がちゃんと払うことで「じいちゃんはじいちゃんの常識を生きただけなんだ」って受け入れたかったのかもしれません。

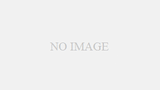

コメント